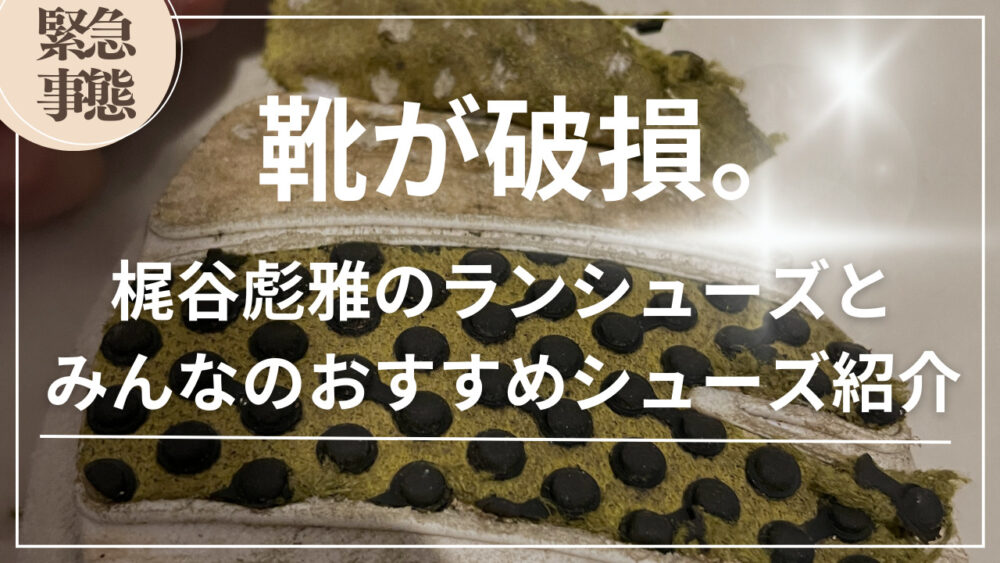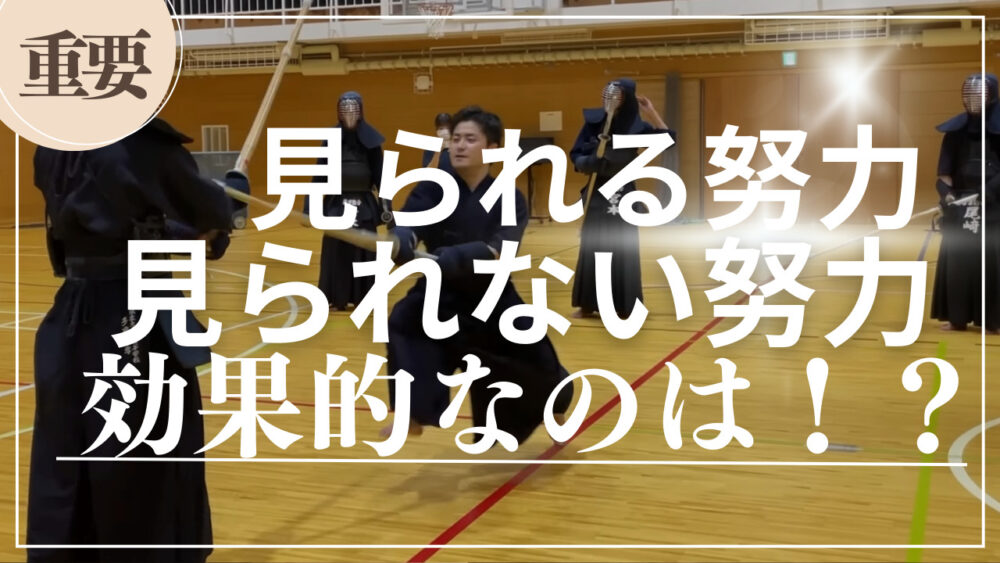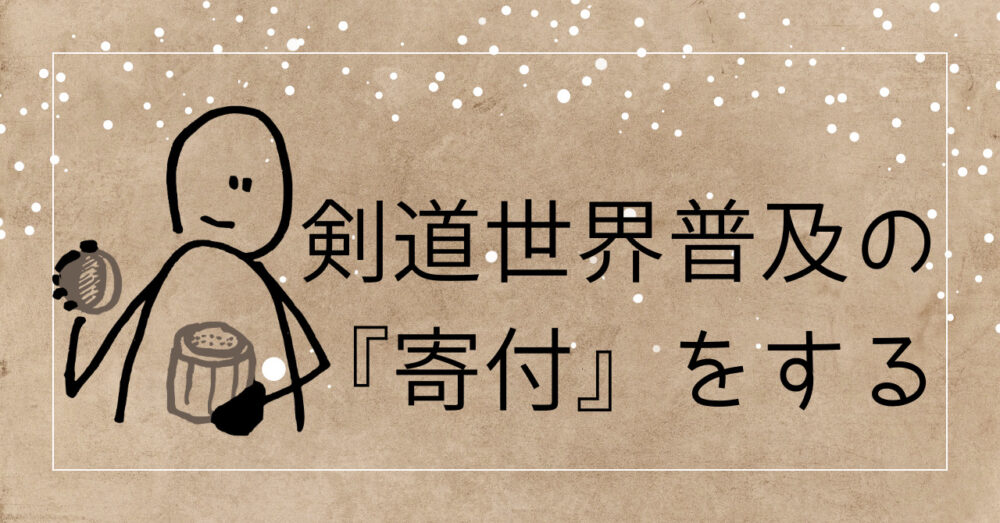『彪雅シリーズ』の竹刀を知っていますか?
高校時代にご縁があって、「製作・改良」に協力させていただいた竹刀です。
現在『彪雅シリーズ』竹刀は全部で11種類が既存しています。
『いや多過ぎ!』
『どれを選べばいいか分からないよ!』
そう感じる人がほとんどでしょう。
しかし、剣道をする上で竹刀選びはとても重要です。
なぜなら『1本を決めて勝利を掴むことができる道具』だからです。
皆さんは竹刀を選ぶ時、何を基準に購入しますか?
また、試合中に下記のような事を感じたことはありませんか?
- 竹刀が重い。
- 使っていると後半疲れてくる。
- 手の内にしっくりこない。
このような悩みも自分に合った竹刀を選ぶと解消されます。
この記事では、『彪雅シリーズ』竹刀の機能を詳しく解説していますので、皆さんも試合で最高のパフォーマンスを発揮する為に、自分にあった竹刀を慎重に選んでください。
選ぶのが面倒!おすすめを購入したい!
「選ぶのが面倒!でも欲しい!」
そんな人は私が使っている『彪雅2』を選んでください。

梶谷彪雅『彪雅シリーズ』竹刀の種類の紹介
『彪雅シリーズ』の竹刀は11種類あリます。
あまりにも多いので先にお伝えしますが『人気シリーズ』は上3つです。
それぞれの竹刀の特徴を詳しく紹介します。
彪雅シリーズ全体の特徴やメリットは竹刀紹介の後に記載いたします。
- BASEで購入
- インスタグラムで5本まとめ購入(DMでお声掛けください)
5本以上購入していただける場合はInstagramで対応しております。
第1位:超実践型『彪雅2』胴張型
『彪雅2』は胴張りの竹刀です。
手元の部分(鍔の上部)を太くする事で、剣先を軽く感じさせる効果があります。
剣先が軽くなる事で「打ち合い」「速い展開」「応じ技」が直刀に比べて苦にならない竹刀です。
先端を軽くすると打突が軽くなってしまう事あります。
しかし『彪雅2』はそんな事はありません。
私は軽さだけを重視して打突が軽くなっては意味がないと思ったので、「胴張り」の特徴を生かしつつ「剣先が落ちる」ような特別な削り方で製作してもらいました。
- 速い試合展開をする選手
- ストレートより「変化技」「応じ技」を多用する選手
- 軽く感じる竹刀を振りたい選手

第2位:直刀型『彪雅』37〜39サイズのみ
『彪雅』は直刀の竹刀です。
重心が手元にある「胴張り」と違い、先にしっかりと重みがあるので強い打突をすることが可能です。
剣先が重い分、腕力が胴張り竹刀より必要な竹刀です。
その分、爆発力や強い打突力ができるので扱えるようになれば胴張型竹刀より1本になる竹刀です。「打ち合い」や「速い展開」の選手と対戦しても勝つ為に鍛錬を重ねましょう。
個人的見解ですが、「警視庁」の方々は直刀を多用しているイメージです。
- 力強い打突にコミットする選手
- 変化技よりもストレートの技を多用する選手
- 先が重く、振った時に落ちる感じが好きな選手

第3位:実践型『彪雅煉獄』胴張型
燻して作られた薫竹(くんちく)は炭素が表面に付着することで黒みを帯びています。
燻す際に炭素が入ることで水分が飛び、竹が引き締まるので強度が増します。
強度が高くなる事は、竹刀の割れにくさに繋がります。
通常の竹刀と比べて薫竹は特殊な色味があるので、見た目がとても格好良いです。
また、少し暗い道場や床色が暗い大会会場だと、竹刀色が同化して見えにくくなる傾向も特徴のひとつです。
体の初動は隠すことが出来ませんが、竹刀の軌道を見えにくくする特徴があります。
他の竹刀と見た目が異なる渋い黒色竹刀を使いたい時は、”薫竹”の彪雅『煉獄(れんご く)』 がおすすめです!
燻竹(バイオ竹刀)に隠された秘密
燻竹(バイオ竹刀)は強度が増すことによって、竹刀のしなりを軽減します。
全日本選手権で優勝された『高鍋選手』の秘話があります。
通常の竹刀は柔らかいので『ここで面だ!』と思っても一瞬曲がってしまうので竹刀が遅れて面に到達するそうです。
しかし、燻製(バイオ竹刀)であれば炭素が付着して強度が増しているので、イメージ通りに『ここで面!』と思ったら、竹刀が遅れて到達することなく面を打突することができるそうです。
竹刀の強度を増すことで割れ防止だけでなく、しなりの軽減にも繋げてみてください!

最安制作:『彪雅Jr(ジュニア)』小学生限定モデル
彪雅シリーズは基本的に「右手小判型」となっています。
しかし右手小判型の高価な実践型竹刀に手が届かない人もいると思います。
そこで『両手丸型』の通常竹刀にする事で彪雅シリーズ最安価格となりました。
「普通の竹刀で良くない?」
と疑問に思った人はちょっと待ってください。
彪雅シリーズの竹刀職人は『バランス』を作るのが非常に上手いんです。
通常は見た目や形を整えて武道具店に並べなれますが、第一にバランスを考えて制作してくれます。なので多少隙間ができてしまうこともあります。
私は見た目は全く気にしません。
とにかく使用感!とにかくバランスが良い竹刀を求めています。
両手丸型ですが、職人さんが『彪雅シリーズを小学生の人にも沢山使って欲しい!』という思いで、1本1本バランスだけを整えて丁寧に制作している竹刀となっています!

並竹を使用した『彪雅0式』
『彪雅2』と『彪雅0式』は同じ「胴張り型」の竹刀です。
「並竹」という平らな竹から作る事から削りが難しい竹刀となっています。
『彪雅0式』の方が若干柄太仕様です。
どちらもバランスが取れた竹刀で、明治大学の池内選手(九州学院出身・現在Panasonic在籍)も『彪雅2』ではなく『彪雅0式』を愛用してくれています。
私も練習用・試合用として『彪雅0式』を愛用しています。

柄太仕様『彪雅3』胴張型(左手28mm)
『彪雅3』は『彪雅0式』よりさらに柄太仕様となっています。
新規格検量になり、剣先がかなり重くなりました。
そこで今までの『彪雅シリーズ』より柄太にすることで、さらに重心を手元に持ってきました。
その分剣先が軽く感じるので、柄太の方が好みの人は彪雅3がおすすめです。
柄太仕様『彪雅3』デメリット
柄太にする事でのデメリットもあります。
- 手が小さい人は握りが浅くなる
- 通常の竹刀より握力の消耗が激しい
軽く感じるのが好きな人におすすめですが、デメリットを把握しておきましょう。
特に手が小さい人は竹刀を落として「反則」を貰い、不利な状況になる可能性があるので注意しましょう。
疲れた時、竹刀を離さないように無理に力を入れて「クソ握り(正しくない握り)」になります。
そのデメリットの軽減に彪雅シリーズの特徴である「右手小判」が機能してくれます。
- 柄太の竹刀が好きな選手
- 少しでも先を軽く感じたい選手
- 柄太で疲れて竹刀を落とす選手

超極太仕様『彪雅Phantom』左手30mm
『彪雅Phantom』は『彪雅3』を超える柄の太さとなっています。
基本的に『彪雅シリーズ』は私の手に合わせた『彪雅』や『彪雅2』『彪雅0式』を作りました。
しかし、手が大きく、もう少し柄を太くして欲しいという人がいたので、『彪雅3』が誕生しました。
さらに本格的な柄太の為に製作したのが『彪雅Phantom』です。
私の感想は「太すぎるし、軽すぎる」ですが、これが好きな人にはリピートが多い竹刀です。…要は自分にあっていればよいのです(笑)
- 『彪雅3』より太い柄を使いたい選手
- 剣先がとにかく軽い竹刀を使いたい選手
- 手が大きい選手
八角型が誕生『彪雅Final』
『彪雅final』は「右手八角小判」+「左手八角」となっています。
複雑な削り方なので、納期に時間が掛かってしまいますが、手のフィット感がある竹刀となっています。
- 竹の素材 :「真竹」のみ製作可能
- 竹刀サイズ:「39」のみ製作可能
- 竹刀の形状:胴張り型で先軽仕様
デメリットとしては、八角と右手小判の両方の削りをしているので、製作が難しく、素材も真竹を使う為、価格が少し高いことです。
金額は気にせず、「八角」+「右手小判」で勝ちたい人は購入検討してみてください!
- 「八角」+「右手小判」を使いたい選手
- 手のフィット感がある竹刀を使いたい選手
- 金額をあまり気にしない選手
左手八角+右手小判型『彪雅Final2』
『彪雅Final』は両手が八角型でしたが、右手のみを小判型の竹刀です。
振ってみた感じは「軽い」「フィット感がある」「右手はいつもの右手小判で使いやすい」です!
美味しい二郎ラーメンに「油増し」「野菜増し」しても、美味しさは変わらず満足度はアップするあの不思議な現象です。
それなのに彪雅Finalより安価な竹刀となっております。1本制作するのに1時間以上かかる代物です。理解するのに1年から2年くらいかかりそうですが、彪雅シリーズの『名刀業物』です。

上段特化型『彪雅JD(ジョーダン)』
彪雅シリーズは基本的に中段選手を意識して制作されております。
そもそも上段用の竹刀も少ないと思っています。
通常の竹刀に少し長めの柄革で使うことが一般的でしょう。
しかし両手で打突するのと「左手1本で打突する」では、竹刀の操作方法が全然違います。
片手で打突しても重さを感じにくくした竹刀が『彪雅JD(ジョーダン)』です。
私は基本的に右手で押し込む事が多いので右手小判が好みですが、左手中心で操作する人は彪雅ジョーダンが中段でも使いやすいという声を頂いています。

竹幅を拡張した『彪雅轟』
竹刀を超越した古刀型の竹刀となっております。
竹幅が広いため見た目がとにかくゴツいです。
特徴は中心の取り合いがかなり有利に試合運びができ、ゴツいわりには振りやすく万能竹刀になります。
- 真竹での製造
- 39男子38男子対応
- 左手25.5前後

『彪雅シリーズ』竹刀の特徴
最後に『彪雅シリーズ』の機能的な特徴を詳しく紹介します。
竹刀の形状は普通の竹刀同様「直刀」と「胴張り」の2種類です。
何度か単語が出てきましたが、どちらも「握り」の右手小判が他の竹刀との違いです。
- 握り
- 右手小判
- 右手小判のメリット・デメリット
- 左手が小判では無い理由
について解説していきます。
1.普通とは全く違う『握り』
私が竹刀を選ぶ時に1番意識しているのが「握り」です。
“彪雅シリーズ”の竹刀ではその“握り”が最大の特徴となります。
練習中や試合の後半、人は少なからず絶対に疲れてきます。
無限の力がある人は別ですが、そんな特殊能力を持っている人はいないと思います。
そこで、力強い打突を試合の終盤まで落とさないようにする為に、何か良い方法は無いかを考えました。
そこで思い浮かんだのが【右手小判】の“握り”です。
2.『右手小判』の圧倒的メリット
- 右手小判って何?
- どんなメリットがあるの?
と疑問が浮かぶと思うので説明していきます。
“右手小判”右手の握り部分が木刀のように、縦長になっています。
このため、試合後半握力が無くなって来た時にも、上から握ることができ、正しい持ち方維持したまま竹刀を振る事ができます。
3.右手小判のメリット・デメリット
最後に『右手小判のメリット・デメリット』について簡単にまとめて終了します!
- 無駄な力を入れずに打突できる
- 小手打ちも自然と刃筋の通った打突ができる
- いろんな角度で放つ引き技も、刃筋の通った打突ができる
- 疲れていても力強い打突ができる
ただ『右手小判』を真似した商品を使ってみましたが、決して良い竹刀とは言えないのが正直な感想でした。おそらく右手だけを削っているのでしょう。
右手小判にした上で『バランス』を1本1本整えなければ粗悪品となってしまうので、彪雅シリーズの類似品で「使いにいくい」と思って、彪雅シリーズの悪い印象を持たないでくださいね笑
- 竹刀が破損した時に組み替えが面倒
- 値段が高価になる
- バランスを整えないと重い竹刀になる。
→手元を削るから先が重くなる。
デメリットの1つ目、「破損した時の組み替え」についてですが、竹刀は4枚の竹の「左右は左右」で組み替えて、「上下は上下」で組み換える必要があります。
そうしなければ、小判型にならないので注意が必要です。
左手が小判ではない理由
「なぜ左手は小判じゃ無いのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
今まで先生に「打突する瞬間だけ力をいれろ!」と言われた経験はありませんか?
「右手は力を抜いて握り、打突の瞬間だけ」力を入れた方が強い打突をすることができます。
しかし、左手まで力を抜いてしまうと振り遅れたり、相面や出鼻小手で出遅れてしまいます。簡単な話をするので「イメージ」してみてください。
左手or右手『片手』で竹刀を振ると想定
- 左手の位置で竹刀を振る場合
- 右手の位置で竹刀を振る場合
あなたはどちらの方が力を使いますか?
A.(答え):左手の位置で持つ方が重心が前にかかるので、「左手だけで竹刀を振る場合」の方が力を使います。
「右手位置で竹刀を振る場合」の方が軽く感じ、力は使いません。
つまり、左手は力を緩めることがありません。
「打突の瞬間でだけ力を入れろ!」というのは両手ではなく、右手だけの話になります。
左手の握りを緩めると、竹刀に力が伝わるまでに時間がかかるので注意しましょう。
右手の力を抜くときも注意が必要
「力を抜く」=「手の内を緩める」と勘違いする人がいます。
そうすると、竹刀と手の内の隙間が出来てしまうので、握るまでに時間が掛かってしまいます。
“握り”は手の内と竹刀に「空間(隙間)」ができないようにしましょう。
また、左手の方を削り落さない分、重心が手元に来ます。
つまり、先を軽く感じることが出来る上に、手元を削らない分で先を削ることが出来ます。
これによって、更にバランスがしっかり取れた竹刀になります。
『彪雅シリーズ』剣道竹刀:まとめ
この『彪雅シリーズ』は一本一本丁寧に削られています。
工場での大量生産ではありません。
※よって全てが完全に同じバランスになるとは限りません。
普通の武道具店では手にすることが出来ない限定竹刀となっています。
- BASEで購入
- インスタグラムで5本まとめ購入(DMでお声掛けください)
5本以上購入していただける場合はInstagramで対応しております。
注文殺到の場合発送が遅れる事があります。
ご理解の程宜しくお願い致します。
最後までこの記事を見ていただき、ありがとうございました!
試合用の竹刀『抜刀斎』『牙突』について知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。
竹刀の「素材」や「形状」の解説や「値段ランキング」や「実践型」ランキングはこちら